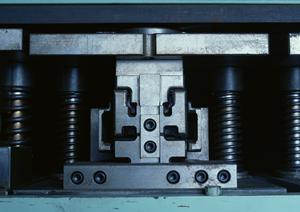赤外線ヒーターの歴史と近年の傾向
赤外線ヒーターは、物質を直接加熱せずに周囲の空気を暖めることで暖房を行う機器です。
この技術は20世紀初頭に開発されました。
最初の商品は、フィリップス社によって1938年に発明されたものです。
このヒーターは発熱体が放射する赤外線によって暖められた、金属製の反射板で構成されていました。
この反射板は、赤外線を反射して広い範囲に熱を放射するように設計されていたのです。
この技術は、第二次世界大戦中に戦時需要によって急速に普及しました。
戦後、赤外線ヒーターは家庭用暖房機器として一般化します。
1950年代には赤外線ランプが開発され、より効率的なヒーターが実現されました。
また1960年代には新しい素材と技術が導入され、より小型で高効率なヒーターが開発されるようになったのです。
近年では、エコロジーに配慮した環境に優しいヒーターが開発される傾向が強いです。
例えば天然ガスを燃料とするヒーターは、CO2排出量を削減して省エネ効果も期待できます。
太陽光発電を利用して、電力を供給するヒーターも登場しているほどです。
この業界は競合他社も多いので、企業イメージも売上に影響してきます。
よりサステナブルなものを開発することで、イメージアップにつながることでしょう。
環境にも良いということならば、消費者にとってもメリットの高い傾向です。
総じて赤外線ヒーターは独自の技術により、従来のヒーターよりも効率的で環境にも配慮された暖房機器として、ますます注目されています。